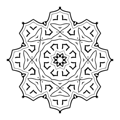寿命と呼吸
ヨガを始めた約20年前、「生涯の呼吸数は決まっているので、1回1回の呼吸をゆっくり大切にすると寿命が延びる」と聞いたことがありました。
私は長生きしたい訳ではないので(楽しく濃く短くタイプ)特別心に刺さらず…。
小さい頃から音楽に携わっていたので深い呼吸が身についている私は長生きするのか?
では日常的に激しい運動をしている人は呼吸数を早く使い切ってしまうので短命なのか?と思っただけでした。
最近また心拍数と寿命の話を耳にすることがあり、改めて調べてみました。
まず呼吸数と心拍数がややこしいですが、1回の呼吸で心臓は4回拍動するという比率があり、呼吸の仕方によって心拍数は変化するという関連性があります。
哺乳動物の総心拍数は一生で20億回説
『哺乳類はどの種であっても一生の間に心臓は20億回打つ』という計算方法があるそうです。
よく例に挙げられるのはネズミとゾウ。
⚫︎ハツカネズミの心拍数は1分間に約600~700回(寿命は2~3年)
⚫︎ゾウの心拍数は1分間に約30回(寿命は約70~80年)
呼吸や心拍がゆったりしている大きな動物ほど寿命が長いようです。
人間はというと、安静時の心拍数は1分間に60~100回なので、人間の生物学的な本来の寿命は55歳程度とされています。心臓は再生しない消耗品で、使った分だけ劣化するのでこのように考えられています。
寿命が延びる要因
ただ実際には栄養状態、衛生面の変化や医療の進化もあって人間の寿命はどんどん延びているので、様々な要因があって寿命は変わり、一概に心拍数だけでは語れません。
寿命が延びる要因の一つとして、2022年4月『ネイチャー』(イギリスの科学雑誌)にある論文が掲載されました。寿命が2年のハツカネズミと30年のハダカデバネズミを比べると、ハツカネズミの遺伝子の変異率が10倍程度高い(壊れやすい)ことがわかったそうです。寿命もハダカデバネズミはハツカネズミの10倍長いです。
人間はというとゲノムはハダカデバネズミよりも更に変化しにくく壊れにくく、寿命は3倍弱長い。ということで遺伝子の変異率が低い(ゲノムが壊れにくい)と細胞の機能は落ちず、ガンにもならず、長生きになるようです。
また、自律神経の乱れ、ストレスや過労が心拍数を高く(呼吸を速く)させ、心疾患、脳卒中、心筋梗塞のリスクが高まるというデータもあるので、意識的に深くゆったりした呼吸をすることで自律神経のバランスを整えることは、寿命にも大きく関わってきます。
自律神経は呼吸、血行、腸内環境など全身の機能を司っているので、自分でコントロールできる呼吸を是非利用してください。
寿命はアムリタ(甘露)で決まる
さて、ヨガではどう考えられているかというと、寿命を決定するのは『アムリタ』であるとされています。
アムリタは『神々の酒』と言われ、これを飲んだ神々は不老不死と無限の力を得るとされていて、のちに甘露と訳されるようになりました。
ハタ・ヨーガでは、アムリタ(甘露)は額の奥にあるアムリタ・チャクラから分泌され、喉のチャクラからぽたぽた1滴ずつ腹部に落ちているとされています。
そしてお腹のチャクラにあるアグニ(消化の炎)によって燃やされて私達の生命力になっています。つまり、アムリタが尽きるときが命が尽きるとき。
このアムリタのぽたぽた…を止める為に、ヨガでは逆さまになるポーズ(シールシャ・アーサナ、サルヴァーンガ・アーサナ)などがあり、これを行うヨーギは不老不死や解脱が叶うとされています。
根が上、枝が下の逆さ菩提樹は不滅なり
アムリタ・チャクラは有名な7つのチャクラには含まれていません。
額の奥にあるこのチャクラは如意牛(ガーヤトリー)という神獣の住処。
その神獣の4つの乳首からアムリタが流れているとされていますが、現代で言うならば、アムリタの分泌はヨガや食事、そのほか嬉しい!楽しい!気持ちいい!幸せ!という感情で促されます。
生きている限り、必ず死は訪れます。
諸行無常を受け入れて一瞬一瞬を生きることに意識を向けると、寿命に対する考え方も変わりそうです。